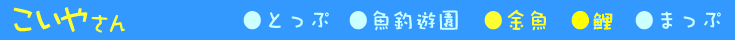
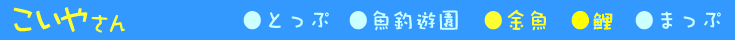 |
||
| ■選び方 |
・丈夫で飼いやすい品種から |
||
| ■移し方 | 急激な水温の変化に弱いので、持って帰ったビニール袋のまま水槽にしばらくつけておき、水温差が2度以内にしてから静かに放します。また、たくさん入れ過ぎてはいけません。 | ||
|
■エサの与え方 |
胃が無いので少しずつしか食べられません。口の大きさに合ったエサを選び、約5分で食べ切る量 を1日に1〜3回与えます。(夏:3回、春秋:2回、冬:1回くらい)エサの与え過ぎは、食べ残しで水が濁ったり、食べ過ぎで脂肪太りになり、病気になり死んでしまう原因となります。 | ||
| ■差し水のやり方 | 水温の上昇による酸素不足でハナアゲをしたら、差し水をし、風通
しのよい所に置きます。 まず、くみおきの水かハイポ2粒をとかした水を入れ、次に加えただけ底の方から水を吸い出します。 |
||
| ■水換えのやり方 | 底の方から溜まっている汚れと一緒に半分だけ古い水を棄て、次に同じ水温の新しい水を加えます。 | ||
| ■水を取り替える回数 | 暖かい時季は、エサをよく食べ、水の汚れも早いので、こまめに水を取り替えましょう。 ・夏季 :毎週1回くらい ・春秋季:2週間に1回 ・冬季 :1〜2ヶ月に1回 また、年に1度は池や水槽をからにして大掃除をしましょう。初夏や初秋に行うと良いでしょう。 |
||
| ■魚や水草の手入れ |
・食べ残したエサは水を悪くするので、早めにすくい取りましょう。(スポイトや、茶漉しなど) |
||
| ■主な病気 | 魚は病気になると治療しにくく、簡単に死んでしまいます。日頃から病気にかからないように予防に勤めることが大切です。 | ||
|
病名
|
症状
|
治療方法
|
|
| 外傷 | 体やヒレが傷つき、傷口から細菌や病原虫が感染します。 | 市販の外傷用薬剤を患部に直接ぬ って消毒するか、エルバージュで薬浴させます。 | |
| 水カビ病 (綿かぶり病) |
体表やヒレにうっすらと白い綿毛がくっついたような状態になります。 | マラカイトグリーン、メチレンブルーなどで薬浴させると効果 があります。 | |
| 白点病 | 体表やヒレに白点がポツポツと発生します。 | イクチオフチリウスという病原虫が寄生して起こります。この病原虫は高温に弱い特徴を利用して、ヒーターなどで水温を徐々に上げ、30度近くにして、2,3日そのままにすると駆除されます。また、市販のニューグリーンFなどの白点病治療薬も効果 があります。 | |
| ちょう | ウオジラミが体表について、体液を吸い、魚は衰弱します。 | きれいな水に市販のマゾチンを点液し、薬浴させます。 | |
| イカリムシ病 | 鱗や、下ヒレに10ミリ位の糸状のイカリムシが寄生し、充血して腫れ上がり、ひどい時は出血します。 | 水温が15度以上になると発生しやすくなります。ピンセットで取り除くか、専用の市販薬で駆除する方法があります。 | |
| 白雲病 | 白濁の斑点が体表にひろがります。 | 水にメグホンを溶かし、1週間に1度30秒間泳がせます。 | |
| 感冒 | 急に水温が大きく変わると、金魚が粘液の白い膜で覆われたようになり、動きも不活発になります。 | 水温を徐々に上げ、25度くらいを保ち、栄養価の高い餌を与えて体力を回復してやります。 | |
| ガス病 | ヒレなどに気泡が入り、破れて切れてしまいます。 | 水温を一定に保ち、水槽に日覆いをしてやります。 | |
| 立鱗病 | 水が汚れると、細菌により体がむくみ、鱗が逆立ちマツカサのようになります。金魚が比較的よくかかる病気なので、注意が必要です。 | 治療が難しいので、予防が大切です。もし、発見した場合は、隔離するとともに、パラザンLなどを餌とともに与え、食欲がない場合は、パラザンDで薬浴させます。 | |
| 水カビ病 | 外傷や水温の激変が原因で金魚の懐死した組織にサプロレグニアという水生菌が付着し、体表やヒレがうっすらと白い綿毛をかぶったようになります。 | マラカイトグリーン・メチレンブルーなど、水にうすく青い色がつく程度に入れ、薬浴させます。 | |
| 腸炎 | 餌の与え過ぎや不良餌により、よく腸に炎症を起こします。食欲がなくなり、群れから離れて水底でじっとしています。 | 直ちに絶食させることが第一です。アクリフラビン系の溶液で薬浴させてからきれいな水に移し、数日様子を見ます。回復してきたら、消化のよい餌を少しずつ与えます。日頃から餌の与え過ぎには注意しましょう。 | |
| 栄養失調 | 栄養のバランスが悪く、体が弱り、寄生虫などがはびこります。 | きれいな水に移し、餌を新鮮な生き餌に変え、総合ビタミン剤を餌に塗り与えます。 | |
| 尾ぐされ病 | 傷にフレキシバクター・カラムナリスという細菌が感染して起こる病気です。尾やヒレが白くなって溶けたようになります。金魚がよくかかる病気で、他に感染するので、十分注意が必要です。 | 何よりの予防は、金魚に傷をつけないようにすることです。治療法としては、市販のニューグリーンF、グリーンFゴールドや、パラザンDなどで薬浴させます。 | |
| エラぐされ病 | 尾ぐされ病と同じ、フレキシバクター・カラムナリスによりエラの一部が腐ったように変色し、ひどくなると一部が欠けてしまったり、呼吸障害を起こし、食欲もなくなり衰弱死します。 | 第一要因である寄生虫などの発生を防ぐことが肝心です。治療法は、尾ぐされ病と同じです。 | |
| 穴あき病 | 原因は不明。体表に小さな穴をあけたようになります。放置するとしだいに穴が大きくなります。この病気で金魚を死なすことはありませんが治療はしてあげましょう。 | この病気は水温が20度以上になると発生しないので、市販の治療薬で薬浴させ、水温を上げるようにします。 | |
| 転覆病 | リュウキンなどの体型の丸い金魚が仰向けになって泳ぎます。原因ははっきりしませんが、浮き袋に異常が起こったためではないかと考えられています。 | 適切な治療法はないのですが、水温が激下したときに起こりやすいので、徐々に上げて元の状態に戻すと回復することがあります。 | |